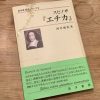「創り出す思考」ワークショップは、すごかった!どうすごかったのかというと、、、
公開日:
緊張構造・構造思考, システム思考, 学習・研修&セミナー, 学習する組織
先日、ロバート・フリッツの最新刊「偉大な組織の最小抵抗経路 ~リーダーのための組織デザイン法則~」が発売になりました
私も、でてスグに書店で購入!
今も、読んでいるところです
「創り出す思考」ワークショップに参加
先週、そのロバート・フリッツが来日し「創り出す思考」ワークショップがあったので、私も行ってきました
このワークショップ、昨年、日本で始めて開催されそのときも行きました
2018年の「創り出す思考」ワークショップの話はコチラ!
→ ロバート・フリッツ 創り出す思考ワークショップに、行ってきました!
同じワークショップで、内容も同じです
でも、でも、、、
衝撃的だったのが、ぜんぜん、ちがった!!!
私の理解ですが、ロバート・フリッツの教えたいことの基本は、
出来事の根底にはすべて「構造」がある
そして、その構造には、前進する「緊張構造」とゆりもどす(よくなったと思っても後戻りして往ったり来たりする)「葛藤構造」がある
いま、自分がどの構造の中にあるのかを見抜いて、根底に葛藤構造があれば、これを緊張構造にデザインしなおすことだ
また、自分が何者か(どんなアイデンティティーを持っているか)は関係無く(どころかこれが足を引っ張ることもある=葛藤構造をつくる)、自分の中にある価値、志から創り出したいものを創ることにフォーカスし、同時に、現実(Reality)をそのまま認識し、現実と創り出したいものの間に緊張構造をつくることで、創り出したいものをつくるんだ
、、、ということです
構造を観るにはPicturingが必須
この中で、私がワークショップに参加して、「難しい!」と思ったのが、創り出したいと思うときの出所、起点が、「価値・志」なのか「(アイデンティティに根ざす)観念」なのかを通常では気づけないということ
そして、現状、どんな構造があるのか?ということを「そのまま」観ることです
この難題を突破する方法も、ロバート・フリッツは提供してくれています
それが、「Picturing」です
もし、自分がコンサルタントで、創り出したいものをつくりたい!と望むクライアントがいるとしたら、まず、現状の話を聴きますよね?
それを、映像化して聴く(観る・考える)のです
絵で聴くっていうと初め何かな?と思いますが、話の内容をすべて映像(ムービー)で聴きます
ロバート・フリッツは、これは練習すればできるし、Picturingが構造思考の基本であり必須のテクノロジーだ!と言います
Picturingは、話されることがすべて映像で観ることで、出来事の構造が見えますし、矛盾点や不明な部分が自然と見えて、そこをクライアント(相手)に尋ねることで、現実がそのまま、それも極めて明確に捉えられます
これは、音(言葉)できくのと段違いです
ただ、このPicturingについては、昨年(2018)のワークショップでも教えてもらいましたし、大事なのはわかりました
やってみようとも思いましたが、結局、その後のフォーローアップや仲間の練習会などのときにするくらいで、普段は、まったくやろうとしませんでした
それが、今回は、ロバート・フリッツが話すこともほとんどすべてPicturingで聴くことができましたし、ワークショップ後も日に、何度もPicturingしています
余談ですが、車を運転しているとき、BGMにかけているサザンもPicturingしています
デジタル意思決定、デジタルビジネス分析もPicturingが基本
ワークショップの中では、デジタル意思決定、デジタルビジネス分析というものも登場します
昨年は、このデジタル意思決定、デジタルビジネス分析と緊張構造などの構造思考は、私には、別々のパーツに見えていました
もっというと、なぜ、創り出す思考のワークショップに、これらが必要なのか?と思いました
(ひどいですけど「おまけ?」なんて思ってました ^^;;)
それが、今回、このデジタル意思決定、デジタルビジネス分析という手法も、基本、Picturingしながら行うのですが、そうするとこれらの手法のレベルが全くかわります
そして、構造思考とデジタル意思決定、デジタルビジネス分析が、私の中でつながりました
同じワークショップでも別物だった!
今年も、昨年と同じワークショップ、同じ内容のはずなのに、私にとっては、まったく別物!!といえます
Picturingのこともそうだし、緊張構造を学んでいるとき、普段、社内で使っているあるシートがあるのですが、内容は同じでも、これを緊張構造が分かるように書き換えたら、、、
そう思って、ノートにラフを描いて休憩時間にロバート・フリッツに見てもらったら尋ねたら「そう!これ!!」と考え方を確認できたので、すぐにシートを修正して10月から使えるようにします
これは、ひとつの例なのですが、こんな風に、いろんな変化が現れます
単純に、私が2回目の受講で理解が深まったから、、、ではないのです
同じく参加された方で、今回が初めての方にも、昨年には見られなかった変化があるし、もちろん、私のように2回目の参加者も、「(去年と)ぜんぜん違う、、、」という感想を漏らされる方が多かったのです
なんで、こんなに昨年と違うのかよくわかってませんが、Picturingのこともちょっと理解が深まったし、仕事でどのように使えるか!が掴めたし、実際、使い始めてるし、とにかく、参加してよかった!!
さぁ、今日も、楽しくがんばります!!
関連記事
-

-
スタッフさんのオンラインNVC基礎講座が今日からスタートです!
昨年から、たこ梅のスタッフさんは、NVC(Non Violent Communication / 非
-

-
昆虫や魚の採集は、それがフィールドワークで学びの場になっているようです
日本一古いおでん屋「たこ梅」の 雑用係 兼 五代目店主 てっちゃんです フィールドワークとは デ
-

-
「入門 組織開発 活き活きと働ける職場をつくる」中村和彦 著 を読んでみます
日本一古いおでん屋「たこ梅」の 雑用係 兼 五代目店主 てっちゃんです 会社、お店という組織を
-

-
本日(9/15)、研修のため臨時休業です!スタッフさんと一緒に勉強してきます!!
おはようございます! 「関東煮(かんとだき/おでん)」と「たこ甘露煮」の上燗屋、今年173年目の『
-

-
たこ梅 北店 髙羽さん、分店 北川さんのNVCオンライン基礎講座がスタート!
今回で、7人目、8人目なんです 何がかというと、、、 4月には、道頓堀にある たこ梅本店の和
-

-
「フロー体験 喜びの現象学」(ミハエル・チクセントミハイ 著)と「虫とり」でのフロー体験!
リーマンショックから、売上が下がり続ける、、、という経験をしました 「学習する組織」(ピータ
-

-
3月の店長会議~コロナ騒動の今だからこそできることもある~
今週、3月の店長会議をやってました コロナウイルス騒動でキタもミナミも、以前より人が少ない 話題
-

-
JMAマネジメント 2019年8月号「社員の主体性を活かし、成長する組織」に載っちゃいました!
日本能率協会 JMAさんが出されてる月刊誌に「JMAマネジメント」があります JMAマネジメ
-

-
「U理論の基本と実践がよ~くわかる本」(中土井 僚 著)をいただきました!
2008年のリーマンショックを機にそれまで順調であって売上が下がり続けるようになりました そのとき
-

-
今、取り組んでいる顧客進化を促す仕組みの『盲点』を発見、、、ガビーーン!!
先週、小阪裕司先生の「ワクワク系マーケティング実践術2016」を受け手、一日、勉強していました!