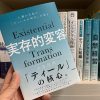自然農法から学ぶティール組織開発を日本初のホラクラシー・ワン認定ファシリテーターの吉原史郎さんに話を聞いてきました!
公開日:
成長・発達, 学習・研修&セミナー, 学習する組織, 働く環境
先週、兵庫県伊丹市へ、自然農法とティール組織の話を聞きに行ってきました
なんで、自然農法とティール組織化というと、、、
ティール組織と学習する組織は相性がいい!
最近、話題になっているのが、英治出版さんから翻訳本が出た「ティール組織」です
ビジネス関係の書籍としては、異例の売れ行きなんだとか、、、
私も、発売と同時に購入して読みました
成人発達理論をベースとした組織の発達段階について書かれています
ものすごく刺激的で面白い本ですので、おすすめです!!
ところで、たこ梅は、リーマンショックから売上が下がり続けたのを機に、百年後も在るために、いろんなこと、想定外のことがあったとしても、それにも向き合って、自ら変化していける「学習する組織」を目指しています
そして、「ティール組織」を読まれるとわかりますが、巷に多くある組織よりも進化したタイプの組織は、学習する組織の要件を備えていることもあって、ティール組織と学習する組織という考え方は、とっても相性もいい!!(って私は思ってます)
自然農法家でありホラクラシーファシリテーターの吉原史郎さん
このティール組織を構築する方法というかやり方の一つにホラクラシーというのがあります
このホラクラシーを提供しているホラクラシー・ワンという会社の日本人初のホラクラシーファシリテーターが吉原史郎さん
吉原史郎さんは、組織開発のお仕事もされているのですが、組織開発というのは、自然農法で野菜を育てることから学ぶことが多い!!と気づかれて、自然農法も研究されています
その吉原史郎さんのパートナーが奥様の吉原裕子さんで、こちらの吉原裕子さんが主体で自然農法に取り組まれています
各々、役割があるんですね
自然農法とティール組織の話を聞きにいった理由(わけ)
吉原さんご夫妻の組織開発の会社はNatural Organizations Labといいます
この会社の自然農法を主体としてやっている部門が、野菜の庭部という部署になります
実は、たこ梅には、家庭菜園レベルですが畑があります
ただ、毎日、手入れできない状況なんですが、以前、吉原さんに在ったときに、「自然農法なら月に1,2回で大丈夫ですよ!」と言われたことを思い出して、ちょっと、話を聞かせてもらおう!と思ってお願いしました
それに、先日、日本人として最初のホラクラシー・ワン認定のホラクラシーファシリテーターの資格も取得されたので、ティール組織なんかのことも一緒に聞きたいと思ってお伝えしたら、「もちろん、いいですよーーーーー!!組織開発と自然農は関係あるし!」と快諾いただいてオフィスのある兵庫県伊丹市に行ってきました
もともと、自然農法とティール組織は、別々に話を聞くつもりだったのが、実は、つながっている、、、関係がある、、、
一粒で二度美味しい、、、ではなく、1回でメチャうま?めちゃラッキー?なのか???
自然農法というは、私の浅い理解でザクっというと、その土壌の様子にあわせて野菜を複数組み合わせることにより、病気や害虫の影響を最低限にして、多様な微生物や生き物の力をかりて野菜が自ら育つようにする農法です
例えば、こんな風に野菜を混栽します

野菜の特性を考えて混栽することで病気や虫が自然と減ります(野菜の庭部さんのサイトから拝借)
すると、周囲の豆が窒素を固定し肥料分を増やしてくれる
ネギとニンニクが虫除けに、、、
、、、というような具合で、各々の野菜が各々の役割を担って、お互いに補完、助け合うことになって、みんな成長する!
それに、混載することで、土壌中の特定栄養分だけが失われることもなく、特定の微生物だけが増えることもなく、連作障害や土壌成分、土壌微生物の偏りを防ぐことが出来るのです
って、これ、組織に置き換えると多様なひとを組み合わせて、、、って似てるでしょ!!
そうなんです!自然農法を学ぶとそこから抽象化した概念は、ほとんど、そのまま組織と人の成長に使えてしまうらしいんです!!
自然農法の畑を見学に!
というようなレクチャーを受けて、実際に、吉原ご夫妻が育ててる、、、というより「見守ってる」畑を見学に行きました!
端境期で、野菜の種類は少ないのですが、ひとつの畝に、数種類の野菜が混栽培されています
そして、その混栽をするために、周囲の畑よりも、ひとつの畝の幅が1.5倍くらいと広くなっています
畑を見学させてもらって、特徴的だったのが、畝で苗を育ててると言うこと
多くの場合、ポットなどの苗床で苗を育てます
専用の苗床ではなく、同じ畝で育てることで、「同じ土なので植え替えたときに活着がいい」んだそうです
ただ、寒冷紗をかけるなどの手間と見守りはされています
上の画像で言うと左上の白い寒冷紗のかかっている部分が、苗用の畝です
その寒冷紗を開けてみると、、、
いろんな種類の小さな苗が、すくすくと育っています
今回、組織開発と自然農法の話とその関連性について話を聞くことができ、これからの たこ梅の人と組織の成長にいろいろ役立ちそうなことが見つかりました
今後、たこ梅の小さな畑のことも吉原さんたちに相談しながら、組織の進化、発達につなげていこうと思います!!
他にも、面白いこと、思いついちゃったしね、、、ぐふふふふ、、、(^o^)v
関連記事
-

-
新人の深澤さん、休憩時間に勉強!!、、、してるの?
昨日の夕方、道頓堀の たこ梅本店に寄りました ちょうど、4時過ぎで、休憩の時間です ん?休憩
-

-
システム思考トレーニング実践編に行ってきました!
たこ梅が「学習する組織」創りに取り組む理由(わけ) お店が順調だった平成20年8月にリーマンショッ
-

-
「最難関のリーダーシップ」(ロナルド・ハイフェッツら著)を購入です!
昨日、梅田のお店に行ったついでに、阪急梅田駅下にある紀伊國屋書店に立ち寄りました そしたら、、、
-

-
「ティール組織」(フレデリック・ラルー 著)を購入!
最近、ホラクラシーという組織が流行ってる(?)というか、話題になっているようです 日本の人事部
-

-
サーバントリーダーシップ(ロバート・K・グリーンリーフ 著)を再読しています
ちょうど6年前に、サーバントリーダーシップ(ロバート・K・グリーンリーフ 著)を読んでいました
-

-
ロバート・キーガン教授来日セミナー「VUCA時代に変化を恐れない組織のあり方とは」に行ってきました!
8月に、ロバート・キーガン、リサ・ラスコウ・レイヒーの共著「なぜ弱さを見せあえる組織は強いのか」が日
-

-
「入門 インテグラル理論」やっとこさ読み始めます
4年前の3月にビル・トルバート博士の「行動探究(Action Inquiry)」ワークショップに参加
-

-
「自分を変える気づきの瞑想法」(アルボムッレ・スマナサーラ 著)を買いました!
リーマンショックがきっかけで、学習する組織を目指すようになりました その中で、学習する組織やU理論
-

-
1泊2日の「遊学旅行」、暑かった!おもろかった!楽しかった!!
先週、2日間、全店、お休みをいただいて、スタッフさんと1泊2日の「遊学旅行」に行ってきました! 研
-

-
NASのバックアップ用HDDを16TBに入れ替えます!
それまで10年来使ってきた事務所のNAS(Network Attached Storage)が故障し