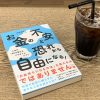「フロー体験 喜びの現象学」(ミハエル・チクセントミハイ 著)と「虫とり」でのフロー体験!
リーマンショックから、売上が下がり続ける、、、という経験をしました
そして、平成22年に学習する組織という考え方に出会い、「これやったら、たこ梅は、百年後もある!」と思って、それ以来、学習する組織を構築しようと取り組んできています
「フロー」を知ったきっかけ
「学習する組織」を目指すようになり、関連書籍や組織開発、人材育成の本を読んでいると、しょっちゅう「フロー」という言葉が出てきます
それで、このフローといわれる状態、スポーツ界では「ゾーンに入る!」といわれる熱中していて、そのプロセスそのものが目的であり、喜びに満たされた状態について研究して発表したのが、ミハエル・チクセントミハイという人というのを知りました
そして、やっと先日から、「フロー体験 喜びの現象学」(ミハエル・チクセントミハイ 著)を読んでいます
フローとは何か?
「フロー」「フロー状態」っていうのは、先にも書いたとおり読む本、読む本で何度もでてきたので、なんとなくはわかっていました
どう、わかっていたかというと
・スポーツで言うゾーンに入った状態
・熱中していて、その行為自体が面白くてどんどんやってしまうと同時にパフォーマンスも高い
・フロー状態になると時間の感覚が通常と異なることがある
(一瞬のできごとが引き延ばされたり、逆に、数時間がほんの数十分程度に感じられたり)
・趣味やスポーツ、好きなことでは、結構起こるけど、(一般的に)普段の仕事ではなかなか起こらないようだ
な感じにわかっていました
わたしの理解はそれとして、本当は「フローとは何か?」については、私が説明するよりも、いま、「フロー体験 喜びの現象学」を読んでいるので、フローに関する記述をいくつか抜き出してみたいと思います
フローに関する抜粋
・フローは自己の統合を促進する。注意が深く集中している状態では、意識は格別良い状態に秩序化されているからである。思考・意図・感情そしてすべての感覚が同一目標に集中している。体験は調和の状態にある。そして、フロー状態が終わった時、人は内的にだけではなく、他者や世界一般に対しても「ともにいる」という感じを、それまでよりも強くもつようになる。
・第一に、通常その経験は、達成できる見通しのある課題と取り組んでいる時に生じる。第二に、自分のしていることに集中できていなければならない。第三、および第四として、その集中が出来るのは一般に、行われている作業に明瞭な目標があり、直接的なフィードバックがあるからである。第五に、意識から日々の生活の気苦労や欲求不満を取り除く、深いけれども無理のない没入状態で行為している。第六に、楽しい経験は自分の行為を統制しているという感覚をともなう。第七に、自己についての意識は消失するが、これに反してフロー体験の後では自己感覚はより強く現われる。最後に、時間の経過の感覚が変わる。数時間は数分のうちに過ぎ、数分は数時間に伸びるように感じられることがある。これらすべての要素の組合わせが深い楽しさ感覚をうむ。
・最適経験の圧倒的大部分は、目標を志向し、ルールによって拘束される活動-心理的エネルギーの投射を必要とし、適切な能力なしには行えない一連の活動中に生じると報告されている。
・フローにこのように完全に没入できるのは、目標が常に明確で、フィードバックが直接的であるからである。
・目標が事前に明確でないいくつかの創造的活動では、自分がしようとしていることについて強い個人的な感覚を洗練しなければならない。画家は完成した絵のできばえについて事前に視覚的イメージをもつことはできないだろう。しかし絵があるところまで進むと、画家にはこれが自分が達成しようといているものか否かが分かるはずである。そして描くことを楽しんでいる画家は内面化された「良い」「悪い」の評価基準をもっているはずであり、一筆ごとに「そうだ、これだ。いや、これは違う」ということが分かるのである。このような内面的な指針なしにはフローを体験することは不可能である。
・我々が働きかけるフィードバックの種類それ自体が無条件に重要であることはあまりない。テニスボールを白線内に打ち込む、相手のキングをチェス盤上で動けなくする、または治療時間の終わりに患者の目に理性のかすかな光を認める。それらの間に何の違いがあるというのだろうか。そこに含まれている象徴的なメッセージ、つまりは私は私の目標を達成できたということが、この情報を価値あるものにする。このような認識は意識の秩序を生み出し、自己の構造を強化する。
・フロー体験を構成する要素のうち、最も数多く挙げられるものの一つは、フローの継続中は生活の中での不快なことのすべてを忘れることができるということである。フローのこの特徴は、楽しい活動は行っていることへの完全な注意の集中を必要とするーしたがって現在行っていることに無関係な情報が意識の中に入る余地を残さないーという事実の重要な副産物である。
・楽しさは不愉快なことの多い通常の生活から切り離されたゲームやスポーツ、その他の余暇活動の中にしばしば生じる。人がチェスのゲームに負けたり、趣味を台無しにしたところで別に心配するほどのことはない。しかし「現実の」生活では仕事上の取引に失敗すれば、くびになったり家を抵当にとられたり福祉の世話になったりするこのように典型的には、フロー体験は統制感をともなった状態ーより正確には、通常の多くの生活状況で典型的に現われる統制喪失の懸念が欠如している状態ということができる。
・これらの回答者が実際に表現しているのは、統制しているという現実というよりも、むしろ統制の可能性なのである。バレエのダンサーは転ぶかもしれないし足を挫くかもしれない。また完全な回転など決してできないのかもしれない。チェスのプレイヤーは負けるかもしれないし、絶対に優勝できないかもしれない。しかしフローの世界では、完全性は少なくとも原理的には達成可能なのである。
・ここで認識すべき重要なことは、フロー体験を生み出す活動は非常に危険なようにみえても、行為者が失敗の境界をできる限りゼロに近づける能力を高めるように構成されているということである。
・この例が示すように、人々が楽しむのは統制されているという感覚ではなく、困難な状況の中で統制を行っているという感覚なのである。人は保護された日常生活での安全をすすんで放棄しない限り統制感を経験することはできない。結果が不確定であるとき、またその結果を左右することができる時にのみ、人は自らの真に統制しているかどうかが分かるのである。
・人は楽しい活動を統制するという能力に溺れて他のことを顧みることができなくなると、究極的な統制、つまり意識の内容を決定する自由を失うことになる。かくしてフローを生み出す楽しい活動は、潜在的に否定的な側面をもつことになる。それらは心の中に秩序を生み出すことによって存在の質を高めることができるが、他方では自己がある種の秩序の虜になるほどまでに病みつきとなり、模糊とした人生に立ち向かおうとしなくなるのである。
※赤字は、てっちゃんにとって「大事だなぁ~」と思う箇所につけてます。著書に、赤字で示されているわけではありません。
虫とりでのフロー体験
さて、こんな「フロー」ですが、私も、つい、数日前に経験しました
それは、うちの桃侍(ももじ/小学4年生)くんと虫とりをしたときのことです
私、子どもの頃から、虫取りや爬虫類、両生類が好きでよく捕っては飼ってました
もちろん、桃侍くんも虫とりは大好き!!
一緒に捕ってきたカブトムシが卵を産んでくれて、毎年、カブトムシが数十匹かえります(ことしも来月くらいかな?)
先日、ひさしぶりに、桃侍くんをつれて、田んぼで、カエルやイモリ、水生昆虫などの虫とりをしてました
1年ぶりくらいでしたが、カエルはもちろん、イモリやヤゴ、コオイムシなんかもゲットです
おもしろくて、桃侍くんとふたりで、カエルは何匹かわからないくらい、、、イモリは9匹、ヤゴは5匹(だったかな?)、コオイムシは卵を背負ったのと背負ってないのも捕まえました
30分くらいたったと思った頃、奥さんが「あんたら、もう、1時間半になるから、、、」って呼びに来たんです!!
え゛?まだ、30分くらいだと思ってたのに、、、
そのあと、桃侍くんと奥さんと私の三人でお茶をしてました
そのとき、読んだばかりのチクセントミハイの
「フローにこのように完全に没入できるのは、目標が常に明確で、フィードバックが直接的であるからである。」
という言葉を思い出しました
田んぼでの虫とりは、網を用水路につっこんで、ガサガサする
ドロごと畦にあげて、カエルやイモリ、ヤゴ、コオイムシなどが入ってるかどうかを確認する
で、入ってると、「よし!!」となって、次は、どのあたりにするか当たりをつけ、また、捕集に向かいます
これって、目標は「カエルやイモリ、水生昆虫を捕獲する!」と明確で、「網を上げるとスグに何がつかまったか!あるいは捕まってないのか!」がわかるのでフィードバックは直接的です
この時、わかりやすい「フロー状態」だったんだろうと思います
桃侍くんも私も、、、
だから、時間感覚がゆがんで、30分足らずのつもりが1時間半も時間がたっていた、、、
これで仕事がスグにフローになることと繋がるかどうかもわかりませんが、自分が、フローだったことを知っている!体感覚でわかってる!って大事な気がします
仕事でのフローが活用できたら?
もし、仕事でも、このフローが活用できたら?
フローで仕事が出来たとしたら?
仕事は、ずっと楽しくなるし、パフォーマンスも上がってしまう、、、
その中で、その人の能力が高くなるので、同じパフォーマンスを出す状態では楽しく(フローで)なくなり、さらに自らチャレンジ(挑戦)するので、より高いパフォーマンスが生じ、また、その中で、能力が高まり、、、
そんな一見夢のようなことが現実のプロセスとして生じるのだと思います、、、というか生じるのがわかります
そして、それは、いま現在のお店や会社でも起こすことが可能です
ただ、スタッフさんの活動をある側面で見ると「制限」しているルールを簡素化していけば、生じるフローの程度(というのかな?)がかわって、より大きな影響力を発揮するのが、なんでかわからんけど、わかります!(笑)
とはいえ、単純にルールを簡素化するだけの放置プレイ!でもうまく行かない
それは、少なくとも、次のことが満たされた状況に身をおけるようにすることが必要だから、、、
・フローに完全に没入するには、目標が常に明確で、フィードバックが直接的である
・困難な状況の中で統制を行っているという感覚を持っている
・人は保護された日常生活での安全をすすんで放棄しない限り統制感を経験することはできず、結果が不確定であるとき、またその結果を左右することができる時にのみ、人は自らの真に統制しているかどうかが分かる
・・・というところまで、頭で考えると同時に、田んぼの虫とりでフロー体験をしたことを併せて、もうちょっと、どないしたらええんか?考えてみます
今すぐわかんなくても、考え続けます
モヤモヤするけど、経験上、モヤモヤしていると、あるとき、突然、わかったりすることもあるので、、、
では、今日も、楽しくがんばります!!(^o^)v
関連記事
-

-
「はじめてのスピノザ 自由へのエチカ」を読んで
日本一古いおでん屋「たこ梅」の 雑用係 兼 五代目店主 てっちゃんです この前、このブログで、
-

-
意図に立ったコーチングは、課題を生む構造そのものを変えていました!
一昨日は、1月最初のコーチング、、、 お昼から、連続で、6名のスタッフさんとコーチングでした そ
-

-
裏庭の自然農法実験畑に野菜20種類以上のタネと苗を植えました!(前編)
奈良の山添村でスタッフさんと自然農法の畑を今年の3月から始めました 自然農法を始めた理由(わけ)そ
-

-
「合併企業が思うように一つにならない本当の理由」(中土井僚 著)を多店舗展開している店が抱える課題へ活用するには?
11月に、U理論の翻訳者であり、企業のコンサルティング、組織開発などに取り組んでらっしゃる中土井僚さ
-

-
スタッフさんと客層分析のため、クラウド型の「スマレジ」を見に行ってきました!
いま、たこ梅の各店では、カシオさんのネットレジを使っています もう、5年くらい、もっと?使っている
-

-
サーバントリーダーシップ(ロバート・K・グリーンリーフ 著)を再読しています
ちょうど6年前に、サーバントリーダーシップ(ロバート・K・グリーンリーフ 著)を読んでいました
-

-
「合併企業が思うように一つにならない本当の理由」(中土井僚 著)が届きました!
オットー・シャーマー博士のU理論の翻訳者のおひとりに、中土井僚さんがいらっしゃいます U理論
-

-
チェンジ・エージェント社主催「システム思考実践発表会」でグランプリをいただきました
日本一古いおでん屋「たこ梅」の 雑用係 兼 五代目店主 てっちゃんです たこ梅を私が継いでから
-

-
4枚組のCDで実践する「マインドフルネス瞑想ガイド」(J.カバットジン著)を買ってみました!
昨年の10月31日、11月1日と2日間にわたって、グーグルなどで実践されているマインドフルネス瞑想の
-

-
行動探求の現場での活用についてチェンジエージェントの小田理一郎さんに相談に行ってきました!
うーーん、使える気がするのに、うまく使えてない、、、いや、ぜんぜん、つかえてない、、、 なにがいか